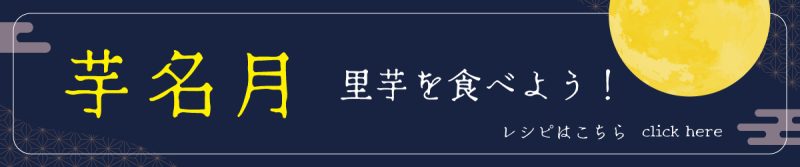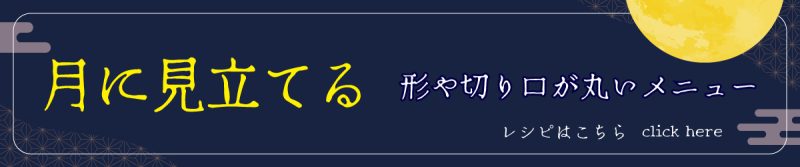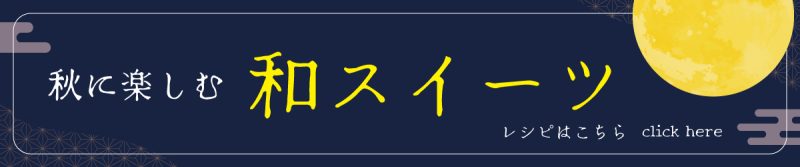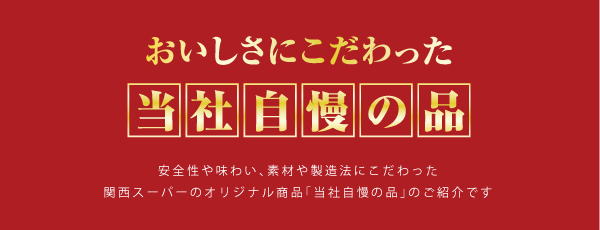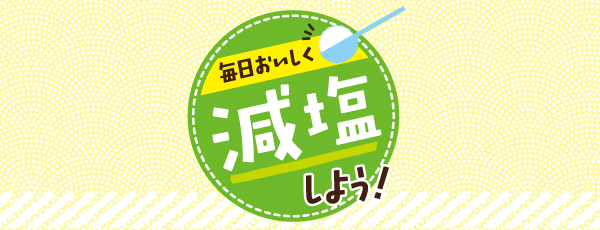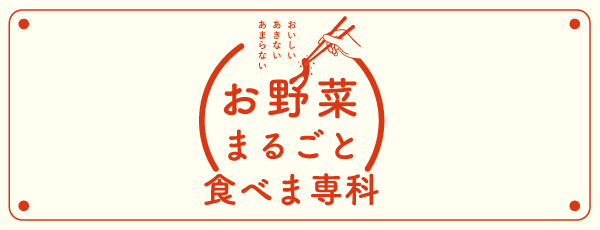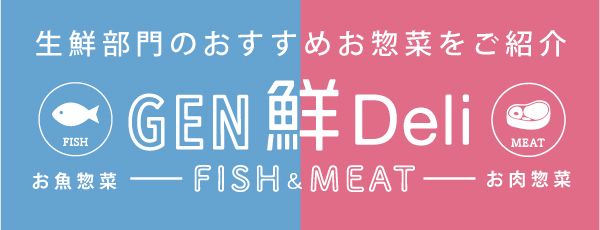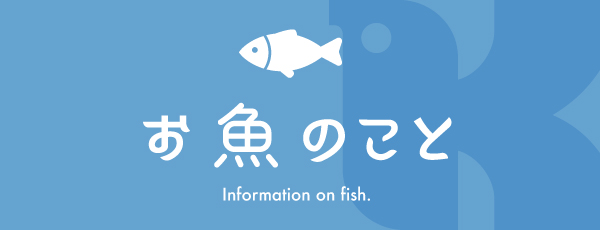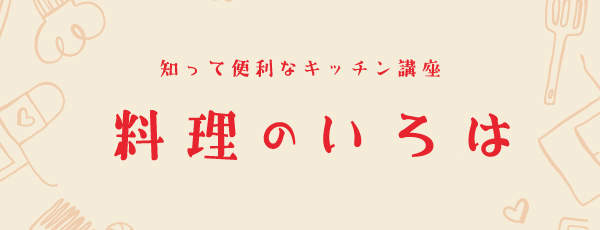HOME
ABOUT
RECIPE
CONTACT
PRIVACY POLICY
News & Topics
キッチンスマイルからのお知らせ
- HOME
- News & Topics
- お月見ってどんな行事?
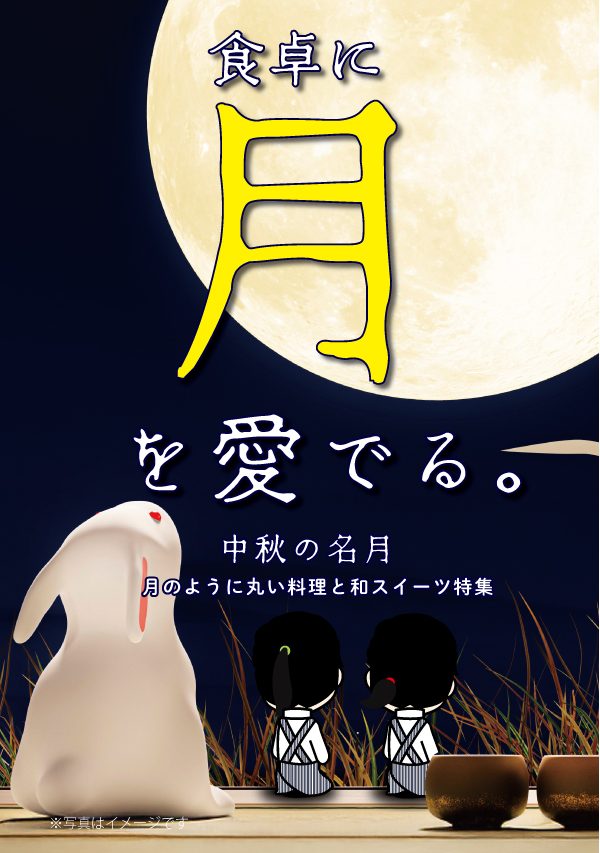
2025.09.07
特集
お月見ってどんな行事?
「お月見」。
皆様は体験したことがありますでしょうか?
その代表が旧暦8月15日に行うとされる「十五夜」。いわゆる「中秋の名月」です。
美しい月を楽しむ行事として知られるお月見ですが、本当のところはどのような行事かご存知でしょうか?
今回は、知ってるようで知らないかもしれないお月見についてご紹介します

そもそもお月見とは?
お月見の起源は中国の「中秋節」にあります。
「中秋節」は。中国の伝統的な三大節句(春節・端午節・中秋節)のひとつで、旧暦8月15日に祝われるもの。
約3000年前、周の時代にはすでに月を祭る儀礼が行われていたとされ、月を愛でながら詩を詠み、音楽を奏で、家族と団らんを楽しむ大切な行事とされてきました。
馴染み深いのは、中秋節の象徴ともいえる菓子「月餅」。
「月餅」は、円形で満月を表すとともに家族の円満や団らんを意味するとされています。
これが奈良時代に日本へと伝わり、やがて平安時代の貴族の間で「観月の宴」として広まり、宮中では舟を池に浮かべ、酒を酌み交わしながら月を眺め、和歌や管弦楽を楽しむ優雅な行事として定着したとされています。
やがて日本ではお月見の風習が、次第に稲作文化と深く結びつき、月を稲の実りを見守る神聖な存在と考え、十五夜が農作物の収穫期と重なることから、「五穀豊穣を祈る日」として位置づけ、お月見はいつしか自然への感謝と祈りを込めた収穫祭の意味合いを強めていったとされています。
ちなみに旧暦では7月から9月を「秋」とし、その真ん中にあたる8月を「中秋」と呼びました。
この中秋の15日にあたる夜の月は特に澄んで美しいとされ、十五夜の月は一年で最も美しい満月として「中秋の名月」と称えることで古くから人々を魅了してきたといわれています。
日本独自のお月見へ
農耕儀礼の一つとして根付いた十五夜は、やがて日本独自の風習としても進化していきました。
「五穀豊穣を祈る日」として位置づけられてきた十五夜では、収穫に感謝し豊作を祈って月に食べ物を供える習慣が広がり、
里芋や栗、柿、梨といった秋の味覚も供え物として用いられるようになります。
十五夜では丸い形が満月を連想させることから特に里芋を供えることが多く、そのことから「芋名月」と呼ぶ地域もあります。後に広がる「月見団子」を供える習慣の原型はこの里芋の供え物だったと考えられています。

そして、お月見に欠かせないのがその「月見団子」。
白く丸い団子は満月を象徴し、十五夜にちなみ15個を積み上げるのが一般的とされ、地域によっては餡入り団子や里芋をかたどった団子を供えるなど、土地ごとの特色も見られます。
また、月に捧げた供え物はその後いただくことで、神様と恵みを分かち合う意味が込められているとされています。
十五夜にはススキを飾るのもお馴染みの光景。
本来は稲を供える習慣でしたが、収穫前で手に入らないことから稲穂に似た代わりにススキを用いるようになったとされています。
ススキには魔除けの力があるとされ、飾った後のススキを軒先に吊るすと、病気や災いを防ぐと信じられてきました。
今日では、お月見は家族で月を眺めながら食卓を囲む季節の行事としても親しまれ、伝統的な月見団子や旬の果物に加えて、食材を満月に見立てた「月見そば」「月見うどん」、「月見バーガー」などといった現代風のアレンジメニューでもおなじみです。
十五夜の後の 十三夜とは?
十五夜とともに十三夜というのみ聞いたことがありませんか?
十三夜とは、旧暦9月13日の夜に月を鑑賞する風習で、実は日本独自の行事とされています。
月齢でいうと、十三夜は満月ではなく少し欠けた月。
この「未完成の美しさ」が日本人の美意識に合い、十五夜と同じくらい大切にされるようになったとされ、十三夜では特に豆や栗を供えることから「豆名月」「栗名月」とも呼ばれています。
また、十五夜と十三夜の両方を愛でることが縁起が良いとされ、両方の月を見ることを「二夜の月見」といい、どちらか片方だけしか見ないことを「片見月」として忌み嫌う地域もあるとか。
十五夜とともに、ぜひ十三夜にもお月見の風習を楽しみ「二夜の月見」を味わってみてはいかがでしょうか?
秋は旬の食材も多く、食欲の秋ともいわれますね。
月を眺めるのは、言わば芸術の秋といった感じでしょうか?
そんな秋ならではの風習を、目でそして味覚で楽しんでみてはいかがでしょうか?