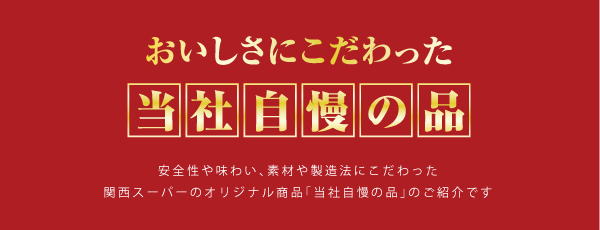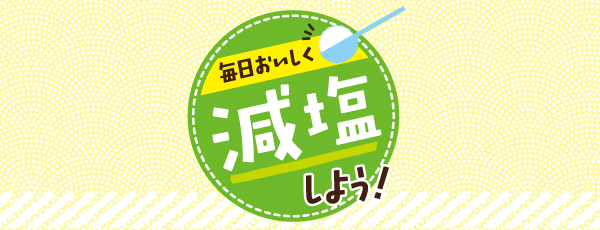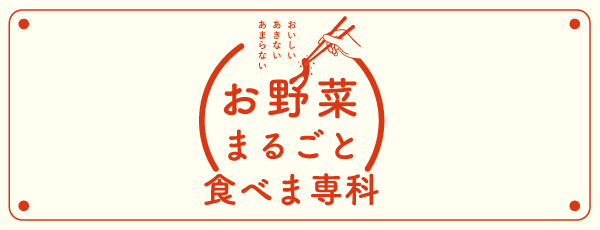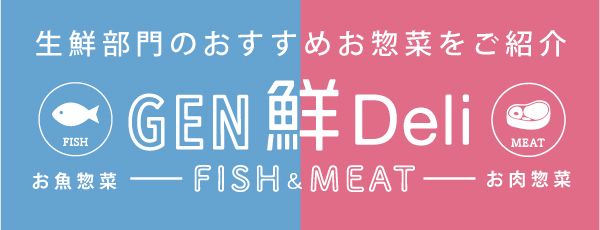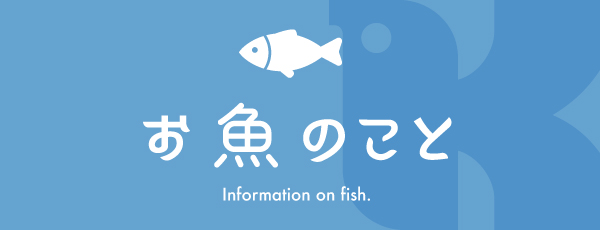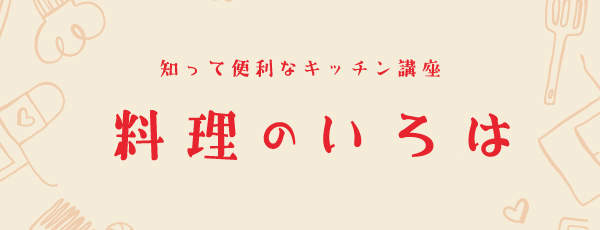HOME
ABOUT
RECIPE
CONTACT
PRIVACY POLICY
News & Topics
キッチンスマイルからのお知らせ
- HOME
- News & Topics
- 七夕に何 食べる ?

2025.06.27
特集
七夕に何 食べる ?
7月7日は七夕です。
半夏生には「たこ」を、土用の丑の日には「うなぎ」を、十五夜には「だんご」を…。
催事には食べ物がつきもの。
では七夕は…?
七夕といえば「笹に短冊」のイメージが強いですが、七夕に食べたい「七夕そうめん」をご紹介します。
7月7日は七夕。
メジャーなイベントではありますが、「短冊に願いを書いて笹に飾る以外はいまいち何をしていいものか…」というかたも多いのではないでしょうか?

・七夕にそうめんを楽しみましょう?
七夕にそうめんが食べられるようになった由来は古代中国からの言い伝えにあります。
古代中国の時代。7月7日に熱病で亡くなった帝の子供が霊鬼神となって熱病を流行らせました。
そこで、生前にその子の好物だった「索餅(さくべい)」をお供えしたところその熱病がおさまった
という伝説からきています。「7月7日に索餅を食べると1年間無病息災で過ごせる」という言い伝えになりました
この索餅は縄のように編み上げた小麦粉のお菓子のようなもので奈良時代に日本に伝えられました。
時代と共に形を変えながら、同じ小麦粉で作られた「そうめん」が7月7日に食べられるようになったと言われています。
これ以外にも、「小麦粉は毒を消す」という言い伝えからとされる説やそうめんを天の川に例えたという説や織物の上手な織姫にあやかり、女の子の裁縫が上達するよう細長いそうめんを
糸に見立てたという説など諸説ありますが、この季節のそうめんには様々な願いが込められているとされています。
そうめんといえば暑い季節に美味しい涼味麺の代表格。
全国乾麺協同組合連合会によって昭和57年から7月7日の七夕の日を「そうめんの日」でもあります。
ぜひ、七夕にはそうめんにちょっぴり願いを込めながら楽しんでみてはいかがでしょうか?
七夕といえば「織姫」と「彦星」のロマンチックな伝説でご存じの方も多いかと思います。
そのロマンチックな話をはじめ、7月7日にまつわる様々な伝説や由来が存在するのをご存じでしょうか?

・七夕のお話とは?
先ずは、七夕の伝説をご存知でしょうか?
ということで、七夕伝説のお話を簡単にご紹介します。
むかし、「天帝」の娘「織姫」と、牛飼いの若者「彦星」がいました。
織姫は天の川のほとりで神様たちが使う大事な布を織っていました。
織姫の結婚相手を探していた「天帝」は、天の川の対岸に彦星という働き者の若者を見つけました。
仕事熱心な若者を気に入った天帝は二人を引き合わせたところ、織姫と彦星はお互いに引かれ合いやがて結婚しました。
ところが、二人は一緒にいることが楽しくて仕方なくなりまったく働かなくなり、いつしか神様の服はボロボロになり牛が倒れて農地を耕すことができなくなってしまいました。
それに怒った天帝は二人を天の川をはさんで離れ離れに。
そうすると今度は二人とも悲しみのあまり泣き続け、仕事どころではなくなりました。
そこで天帝は、二人が以前のようにまじめに働くのならば年に一度だけ、7月7日に会っても良いと約束をし、そしてこの日だけカササギが翼を広げて天の川に橋を架けてくれることとなりました。
それからというもの二人は心を入れ替え、まじめに働くようになりましたとさ。
これが、七夕の織姫と彦星の伝説のお話です。
この織姫と彦星の伝説のはじまりはこちらも中国。
琴座のベガと呼ばれる織女(しょくじょ)星は裁縫の仕事、鷲(わし)座のアルタイルと呼ばれる牽牛(けんぎゅう)星は
農業の仕事をつかさどる星と考えられていました。
織姫とされている「ベガ」と、彦星とされている「アルタイル」は、旧暦の7月7日頃になると天の川の両方の岸に位置し、最も光り輝いて見えると言われ、「一年に一度だけの、めぐり合いの日」として祝われるようになりました。
織姫の父は「天の川」にいる神「天帝」とされ、織姫と彦星は7月7日に天の川を渡って再会を果たすというストーリーと星座の配置が重なることに由来していると言われています。
・七夕の名前の由来
かつて七夕は五節句のひとつとして、宮中では「しちせき」と呼ばれていました。
祖先の霊を祀るため機織りをし、織り上がった布を祖先の霊に捧げるという行事があり、そのときに使われたのが「棚機」(たなばた)」という織り機で、この時に先祖に捧げる布を織る女性の事を「棚機つ女(たなばたつめ)」と呼んだ事が「たなばた」と呼ばれる由来ではないかとされています。
やがてこの行事はお盆を迎える準備として7月7日の夜に行われるようになり、七夕という二文字で「たなばた」と当て字で読むようになったのではないかといわれています。
・七夕行事のいわれ
中国から伝わった行事として「乞巧奠(きこうでん)」というものがあります。
これは7月7日に織女星にあやかって、はた織りや裁縫が上達するようにとお祈りをする風習から生まれましたとされ、庭先の祭壇に針などをそなえて、星に祈りを捧げるもの。やがてはた織りだけでなく芸事や書道などの上達も願うようになったとのこと。
これが平安時代にその話が日本に伝わると宮中行事として行われるようになり、宮中の人々は祭壇を作り、供えものをして星をながめながら香をたき、音楽を奏で、願いを込めた詩歌を梶の葉にしたためて楽しむようになりました。
梶は古くから神聖な木とされ、祭具として多くの場面で使われてきました。
江戸時代になり七夕行事が五節句の一つとなると七夕は庶民の間にも広まり、人々は野菜や果物をそ供えて、詩歌や習いごとの上達を願い、やがて梶の葉の代わりに五つの色の短冊に色々な願い事を書いて笹竹につるし星に祈るお祭りと変わっていったといわれています。
中国には古代より、木・火・土・金・水の五つの要素によって自然現象や社会現象が変化するという説があり、五色のたんざくはこれにちなんだ緑・赤・黄・白・黒で、中国では短冊ではなく、織姫の織り糸にちなみ、吹き流しや五色の糸を吊るします。
これで、馴染みのある七夕イベントの原型が見えてきますね。
7月7日の七夕の夜に織姫と彦星は1年に一度の「再会」という願いを叶えるように短冊に色々な願い事を書いて、笹や竹の葉に飾ります。
織姫と彦星のように、願いを叶えるために1年間一生懸命に努力すれば願いを叶えられるのかもしれませんね。